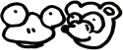稲刈り ほにょ登場

上の写真にある ↓ これ、「ほにょ」。
稲の天日干しの形は様々。岩手、青森、宮城県に多いという「ほにょ」。田んぼに1本の棒を立て、つっかい棒を縛り付け、その上に稲束を互い違いに積み重ねて干す。
人が蓑笠姿で立っているような形。
引用 なまめはぎ pref.akita.jp
語源
稲穂が仁王様のように立っている → 稲穂の仁王 → 穂仁王(ほにお)
という説と
鳰(にお)という鳥の形に似ているから穂鳰(ほにお)
という説あり
なぜに「ほにょ」を?
問題:能登定番の多段・物干し型の稲架掛けで干してきたが、古代米が生命力有りすぎ( TДT)前年の稲架からこぼれ落ちた籾から勝手に発芽してきて困る。
だから、
育苗 → 生育 → 稲架 → 稲藁を田に返す
まで一貫して同じ場所で管理したい。
ということで場所を選ばずコンパクトに干せる「ほにょ」に登場いただいた。
建て方
材料は、3メートルほどの「稲掛木」1本と、「つっかえ棒」3本。稲掛木は刺さりやすいように先を尖らせる。つっかえ棒は沈まないように先を平たいままにしておく。写真で分かるように、外形が30cmほどの長靴の倍程度、稲掛木は地面に60cmほど刺しておく。
「稲掛木」を地面に刺す
稲掛木を、次の動画のようにして突き刺す。稲刈りが終わったばかりの田んぼなら、柔らかいので、こんなんで充分刺さる。
刺しては、こじる。こじるのは、ぐるぐる回すのではなくて、杭を抜くときと同じ要領で次の写真の矢印で示すようにギッタンバッコンする方がよい。ぐるぐるすると、地面の中に堤型の空洞ができて埋め戻すのが大変だ。
こじっては刺すを繰り返すと、逆三角形の穴が空くので、何かで埋めなくては棒は倒れる。この穴は砂で埋めるのが良い。砂は濡れていても締まったままでいてくれて、田んぼの粘土のようにグニャっと変形することがない。
つっかえ棒を結わえる
稲を掛ける始点の作り方には、2大流派があり、短い棒を横にして稲掛木に結わえるのと、私のようなつっかえ棒のとがある。私のとこは風が強くて倒れやしないか心配なので、つっかえ棒を採用している。つっかえ棒はカケヤで軽く打ち込んで、赤い線のところで結ぶ。あとは、つっかえ棒の上にどんどん稲束を積み重ねて行くだけ。
結果
風の谷(強風)の横山で、果たして倒れずに稲を干せるか心配したけど、ドッカン雨風に何の影響もない。ほっ(^。^;)
藁が痛むかなと思ったけど、これも大丈夫。
さらには、建てるのも、しまうのも楽。
今後も「ほにょ」採用。
参考
- リトルフォレスト


この記事が気に入ったら →
いいネ!(SNSアカウント不要で、いいネ!できます。足跡も残りませんので、お気軽に。)